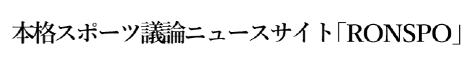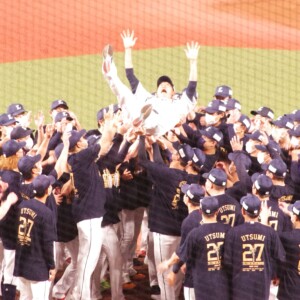「高校野球のDH制と検討中の7回制はスカウトを困らせる」元ヤクルト編成部長が進む“甲子園改革”のドラフトへの影響を懸念「野手の素質を持った投手がその芽を摘まれないか」
沖縄尚学の初優勝で幕を閉じた夏の甲子園は「二部制」が初めて取り入れられるなど改革の大会でもあった。来季はセンバツからDH制が導入され、さらに今秋の国体から実験的に7回制が採用され、議論が本格化する方向。選手の出場機会を増やすことや健康管理を考えての変革だが、元ヤクルト編成部長で、故・野村克也氏の“参謀”としてヤクルト、阪神などでコーチを務めた松井優典氏は「プロ側から見るとスカウト活動に影響は出る。野球界にとって損失が生まれるかも」との懸念を示した。
酷暑対策の二部制は成功したのか?
変革の甲子園だった。
酷暑対策としての「二部制」が1、2回戦の5日間に採用された。1部は午前8時から2試合、2部は午後4時15分からナイターを使用しての2試合。それぞれ終了時間も設定されており、その時間を過ぎて新たなイニングに入らず翌日以降の「継続試合」とされるルールだったが、その「継続試合」は1試合もなかった。
8日の第4試合の高知中央―綾羽は、第1試合が雨の中断で長引き、午後7時49分の試合開始となり、試合は「継続試合」となるメドの午後10時を過ぎたが、応援団の問題などがあるため、両チーム合意の上、臨機応変に延長された。
試合終了は午後10時46分。記録が残る第35回大会以降で最も遅い時間での終了となり、高校生にそんな夜間にまでプレーさせたこと、二部制で観客席がガラガラになったこと、雨天中止の判断を早く行わねばならず、試合の消化に影響が出ることなどの問題点が指摘された。
だが、一方で大会の期間中に熱中症の疑いで医務室に運びこまれた選手の人数は、去年の58人から24人と大幅に減少し、酷暑対策としては成功した。
そして高校野球は新たな改革に踏み出す。DH制が来春のセンバツから導入されることが決定した。選手の出場機会を増やすのが目的。さらに今秋の国体スポーツ大会から実験的に7回制が採用される。その反応を見て、議論を深め、年内にも正式に採用するかどうかの結論が出される方向。こちらは選手の健康管理が狙いとされているが、試合時間を短縮するという高校野球でありながら、興行的な一面が理由のひとつにあることも否定できないだろう。
元ヤクルト編成部長の松井氏は「プロの目線から見るとスカウト活動に支障が出る。ドラフトへ影響を与える変革だ」という見方をしている。
まずはDH制。プロでも、セ・リーグが2027年からDH制の採用を決定したが、高校野球のDH制とは直結しないという。
「今大会もベスト8に残った公立校は県岐阜商1チームだけだった。DH制が導入されると、ますます私立の強豪校と公立校の格差が広がると思う。またチームによっては、投手にバッティング練習をさせないところが出てくるかもしれない。4番で投手という選手が、今後出てこなくなると、プロ側からすれば大問題だ。二刀流ではなく、投手だが野手として評価する選手が少なくないからだ。打者としての素質を持つ投手が高校の段階でその芽を摘まれることになれば、野球界にとって損失になるのではないか」