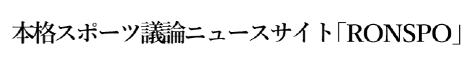相次ぐリング事故のボクシング界の危機にプロとアマが歴史的握手!JBCと日本ボクシング連盟が合同医事委員会を開催…「競技人口の低下につながる事態は避けなければ」
この日の情報交換では事故後の対応策にアマ側から重要なヒントが多く出された。ひとつは病院側の「受け入れネットワーク」の構築。仲間会長の説明によると、アマでは大会ごとに、事前に事故が起きた場合に備えて受け入れてもらえる病院に連絡を入れておき、病院によって、対応の専門医師や手術室がいない場合があるため、複数の病院を順位付けしてリスト化、連絡手順を決めておくという。そうしておけば、救急隊員が搬送先を探す際の時間ロスがなくなり、「10分から20分、搬送する時間を短縮する可能性がある」(仲間会長)という。
プロ側では、救急車両の購入が検討されていたが、協会が、民間の救急車両は信号などの通過ができず、年間の維持費も必要になるなどの問題点を指摘。それよりも先に後楽園に近い病院を受け入れ先として確保することの重要性を求めていたが、このアマ方式であれば、それらの問題も解決する。
またJBCはアマの脳震盪を起こした選手に対する復帰プログラムについても関心を寄せた。アマではKO負けなどで脳震盪を起こした選手は30日間の試合出場停止となり、CT検査などを経て各ブロックの医事委員からのOKが出て、スパーの再開が許可されるなど、実戦復帰までの厳格なプログラムがある。
JBCでも「KO及びTKOした選手が90日を経過しなければ試合出場ができない」というルールがあり、協会は20日の緊急理事会でこの厳守を決めた。これまでは協会の内規でCT検査などを受けた場合に60日でも特別許可されるケースがあったが、今後はそれを廃止、さらに判定負けでも「KO負けでなくともダメージのある試合をした場合は90日の間隔を置いてもらう」との考えを示した。これは協会内規では決定できない事案でJBCへルールの改定を要請するという。
ただアマのように練習再開にまで制限はつけていない。スパーでのダメージの影響が、問題視されており、この練習再開にも厳格な制限をしているアマの復帰プログラムは参考になるだろう。
仲間会長によると「アマの事故が起きるリスクはプロの100分の1」で、医学的な論文があるという。その根拠のひとつが「プロに比べて圧倒的に早いストップ」にいある。アマでは、一瞬動きが止まるなどパンチが少しでも効いた時点ですぐにダウンが宣告される。
この日の委員会では、仲間会長から再発防止に向けてレフェリングの改善と「早めのストップ」が提案された。
「日本の選手は限界まで頑張るだけに、もうちょっと早く止めていいのでは。プロでも20年、30年前に比べてストップが早くなってているが、安全管理がさらに進むと早いと思わなくなる。まだまだ改善の余地がある」
安河内本部事務局長もその意見に同調。
21日に後楽園で開催された「フェニックスバトル141」からレフェリーを集めて「気持ち早くいこう」と指示をしていたことを明かした。
またアマは事故が起きた場合の「報告フォーマット」を改めて整備することを決定したが、プロ側はその義務が果たされておらず、安河内本部事務局長は、練習中に起きた死亡事故と開頭手術の報告を受けていないことを明かした。