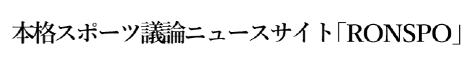相次ぐリング事故のボクシング界の危機にプロとアマが歴史的握手!JBCと日本ボクシング連盟が合同医事委員会を開催…「競技人口の低下につながる事態は避けなければ」
ただ再発防止策についてはこの日は深く議論されなかった。2か月に一度のペースで定例化することで合意した次回の合同委員会でのメインテーマとなる予定で過度な水抜き減量の防止についてもアマ側の意見は重要だろう。
医学的な根拠はないが、過度な水抜き減量で、体内の水分量が減ると、脳脊髄液も減少し、脳と硬膜をつないでいる静脈が外部からの影響を受けやすくなり、出血リスクが上がるとの仮説がある。
JBCは今回の事故を受けて、体組成の測定器を使い、脳内も含めた体内の水分量をチェック、前後にMRI検査も併せて実験的に過度な水抜き減量がどうパフォーマンスに影響を与えているかのデータを集める方針を固め協会側も賛同した。
実は、アマはすでに花王の協力を得て2021年の全日本選手権の1回戦で体組成計を使い体内の水分量をチェックして本人の感覚や結果をデータ化している。
仲間会長によると「体の水分量が下がって減量幅の大きい選手は、体感的に調子がいいと思う選手の率が高いが勝率は低い」という。
JBCは、協会との緊急協議で、過度な水抜き減量に歯止めをかけるため、計量後のリカバリーで、当日体重がリミットの10%以上に増量していた選手に転級を義務づけるルールの導入の検討を提起した。だが、協会側からは「脱水状態のまま試合を行い逆に危険な試合が増える」との意見が出て、即時導入に「待った」がかかった。まずデータ収集を優先することを主張した。
安河内本部事務局長は、「当日に10、12%増えているということは、もっと減量しているということ、それを止めるためのひとつの予防策」と説明したが、そのあたりの意思疎通ができていない。心臓外科医でもある仲間会長はこんな意見だ。
「極端な脱水による臓器障害は1日、2日では元に戻らない。限界超えた水抜き減量ではリスクが上がる。ただ10%に制限をかけると脱水状態のまま試合に出てくる選手も出てきて難しい。戻しに制限をかけるなら、IBFのように当日計量の時間を早くする必要もあるだろうし、日本選手だけがやって海外選手はどうするかの問題がある。アマは、階級が5キロ刻みと、プロに比べて小刻みではなく、当日計量なので、そもそも極端な減量が難しいので、プロとの比較は難しいが、限界まで絞らない風潮になるのが健全だ」
安河内本部事務局長は「水抜き減量にアマも問題意識をもっておられる。トレーナー講習などでもご意見をもらいたい」という話をした。
またプロ、アマ共にアンダー15世代のボクシング大会を運営しているが、そこでも問題が起きていてその安全性を担保するための意見交換も行ったという。
仲間会長にとっても意義のある合同委員会になったという。
「プロは事故が起きた時にどうするかに焦点を合わせていて、その考え方の違いが勉強になった。ドクターの方々もボクシングに特化した知識を持っている。視点の違いからいい意見が生まれると感じた」
この最大の危機を脱するためにはプロもアマもない。JBCは、すでに地域タイトルを12回から10回に短縮することを決定、実施しているが、ボクシング界が一致団結して二度と悲劇が起きないための再発防止プランをスピード感を持って実行せねばならない。