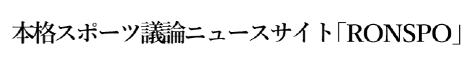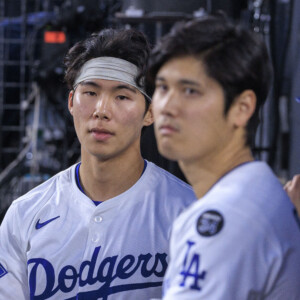優勝した沖縄尚学と日大三の“差”はどこにあったのか…「狙い球の絞り方に疑問」ノムさん“参謀”が戦術から分析した夏の甲子園決勝
矛と盾の構図のゲームだった。
沖縄尚学はミスをカバーするチーム力でチャンスを確実にモノにした。
6回の勝ち越し場面では、先頭の宮城泰成がライト前ヒットで出塁すると日大三は、2番手の山口凌我から背番号1の笑顔のエース、近藤優樹にスイッチしてきた。続く真喜志はバントを失敗、比嘉大登も凡退したが、 4番の宜野座の打席の初球に一塁走者の宮城が盗塁を決めたのだ。リードは小さかったが捕手が送球できないほど、スタートが速かった。
比嘉監督は「足が使える選手。サインというか自分でいけるタイミングで、あそこは覚悟を決めてよく走ってくれた」と振り返った。
サインは「いけたらいけ」のグリーンライト。
松井氏は、「盗塁が考えられるシチュエーション。その前に日大三のバッテリーは1球牽制をしていた。あのスタートの速さは、2球続けて牽制がないなど、なんらかのクセを盗んでいたんじゃないか」と、推測した。
続く4番の宜野座は、初球を三遊間に運んで勝ち越す。沖縄尚学の準備力が奪った勝ち越し点。沖縄尚学は8回にも宜野座が2打席連続のタイムリーで貴重な追加点をあげた。宜野座は準決勝の山梨学院戦から、4番を任されていた。「ずっと勝利打点をあげていた」と、比嘉監督が決断した打順変更がズバリ的中した。
一方で松井氏は沖縄尚学という盾を崩せなかった日大三の戦略に「新垣に対してチームとして狙い球の絞り方に疑問があった」と疑問を投げかけた。
「新垣の投球はストレートがいわゆる見せ球で、スライダーを軸にカーブ、フォークの変化球が勝負球。配球の割合もスライダーが多くストレートは少なかった。なのに日大打線は5回まであまり投げてこないストレートを狙い球にしていた。1回にストレートを狙って先制したが、以降は難しいボールに手を出すことになり、攻略の糸口をつかめなかった。3周り目まで狙い球は変わっていなかった。そこから対応しようとしていたが、配球を追いかける展開になると、もう沖縄尚学バッテリーの思うツボ。日大三の技術と新垣のレベルから考えると、変化球に目つけをしてストレートをカットなどで対応することは十分にできたはず。ベンチの指示も含めて日大は、普段の野球ができていなかった」