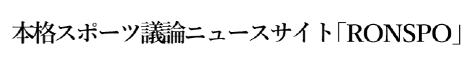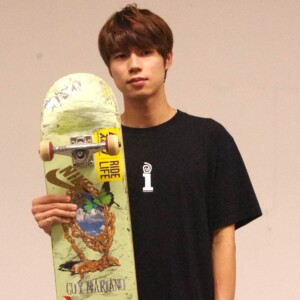世界のマラソントップランナーが集まらない不人気“世陸”で入賞に届かなかった日本男子マラソン界の“トホホ”の現状
東京世界陸上の男子マラソンが15日、国立競技場発着の42.95㎞コースで行われ、日本勢は近藤亮太(三菱重工)の11位(2時間10分53秒)が最高で12年ぶりの入賞に19秒届かなかった。小山直城(Honda)は23位(2時間13分42秒)、吉田祐也(GMOインターネットグループ)は34位(2時間16分58秒)に終わった。フライングや前代未聞の同着など、話題満載の男子マラソンだったが、実は、マラソンに関しては、世界のトップが、今大会に集結していないという裏事情があった。そこでなぜ男子マラソン勢は入賞すらできなかったのか。
賞金&出場料の問題
男子も女子同様に過酷な状況になった。出場者88人中22人が途中棄権。そのなかでジャパン3人の暑熱対策はうまく機能したようだ。
「自分が想像してたよりは暑くなかった」と近藤が言えば、吉田も「暑さに関しては全く問題なかった」と振り返る。「暑さに弱い」と自覚する小山も「ゼネラルの氷を積極的に活用して、深部体温を上げないように意識して取り組みました。そこまでオーバーヒートすることなく走りきれたかなと思います」と話していた。
では、なぜ今回も入賞に届かなかったのか。
まずは純粋に実力が足りていなかったことがある。日本勢の自己ベストは吉田の2時間5分16秒(日本歴代3位)が最高で、今大会の出場者では11番目。なおメダリストたちの自己ベストは2時間4分38秒、2時間4分58秒、2時間6分06秒だった。
そして3人の話を総括すると、今回も微妙なペースチェンジに体力を削られたという。
日本勢は25㎞付近まで大集団でレースを進めた。そのなかで比較的うまく対応したのが小山だ。腕時計をつけずに、「自分が楽に感じるペースをひたすら続けよう」と細かなペース変化には反応しなかった。一度は集団から引き離されたが、最終的には38㎞過ぎまでトップ集団に食らいついている。
一方で本人の自覚がないなかで消耗したのが日本勢で最も期待値の高かった吉田だ。
「練習は妥協なく積めたと言い切れますし、世界大会の雰囲気に呑まれた感じもありませんでした。原因はよく分からないですけど、前半からペースチェンジに対応できていなかった。無駄に対応しないように意識はしていたんですけど、少しずつダメージが蓄積された感じです」
そして吉田は25㎞過ぎに先頭集団から脱落した。
ボストンやニューヨークシティはペースメーカーをつけないことで知られているが、五輪や世界選手権以外でペースメーカー不在のレースは少なくなっている。しかも東京、大阪、福岡国際という国内メジャーレースは海外よりもペースメーカーがうまく機能している印象が強い。
そのため世界大会に出場した日本人選手は、「想像していた以上にペースの上げ下げがあった」というのが〝言い訳〟の常套句になっている。
だが、今回は例年以上に微妙なペース変化があったようだ。その理由は東京の〝高温多湿〟にある。
世界大会は各国のテーブルがあり、そこでスペシャルドリンク(マイボトル)を受け取ることができる。しかし、酷暑のサバイバルレース。選手たちは例年以上に水分を欲しっていた。ゼネラルテーブルのミネラルウォーターだけでなく、火照ったカラダを冷やすために氷を活用する選手も多くいたのだ。
「3㎞ごとにゼネラルテーブルとドリンクがあったので、そこでダッシュする選手が多かったんです。集団の入れ替わりが激しく、自分もペースを乱されました」と近藤。パリ五輪を経験している小山も「ゼネラルテーブルは片側にしかないので、そこでペースの上げ下げを感じました」と話している。