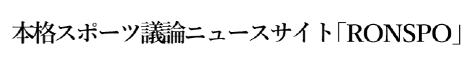「指導者のほとんどが明日はわが身と感じているんじゃないですか」広陵の“暴力事案”が甲子園出場監督に与えたショックと覚悟「2年半は親代わり。選手1人1人のシグナルを見逃さない」
多感な時期の部員を相手に信頼関係を築く難しさを痛感しているからに違いない。今年1月の寮内で起きた暴力事案は、学校側のヒヤリングなどで認定され、加害生徒4人が被害生徒に謝罪したが、被害生徒は3月末に転校した。さらにSNSの実名告発によって表沙汰になった別の事案は、学校側が否定し、第三者委員会が調査中で、被害者生徒が申告した暴力行為は認定されていない。だが、SNSによる実名告発によると、被害者生徒は、所轄の警察署に被害届を提出している。
前述した保護の観点で学校側も日本高野連も2つの事案を公表してこなかった。だが、SNSで拡散後に発表を余儀なくされ、すべて後手に回っている対応や、被害者の訴えとの食い違いを見ると、どこかで「臭いものには蓋」という意識が働き、解決を急ぎすぎてはいなかっただろうかと思わざるを得ない。
もし、そうだとすると大人側の責任は重く、被害部員はその対応に絶望し、加害部員は事の重大さを学ぶ機会を失うことにつながりかねない。
さらに今回の件で深刻なのがSNSでの拡散と情報の信憑性だ。
土井監督も「ネットで一気に広まりどんどん話に尾ひれがつき何が真実なのかが見えにくくなっている」と話す。
また土井監督は、令和の時代の高校野球の指導者の意見として、部員、部員の親、監督の三位一体となることの重要性を強調した。
「今回の件ではなく一般論として言わせてもらいますが、部員、保護者、指導者にどこかで行き過ぎるものがあると、この三者の信頼の正三角形が崩れかねないんです。お互いに冷静に対処する必要があると思います」
熱血漢の土井監督の持論は、「自分がいい人にならなければ、いい人と出会わない」というもの。
「一流の選手である前に一流の高校生であること」を重視しチームでは部員との絆を深めようとしている。
「選手には自分で、ここの野球部でやりたいと思ったのなら何のために野球をやるのか、自覚と責任を持ってもらうように指導していますし、指導する側も野球の前に人間教育が大切と常々思っています。完璧は無理でも互いにそれに近づいていけるようにしたいんです。自身は部員を指導する2年半は親代わりと思っているし、選手1人1人のシグナルを見逃さないように心がけている。それと、大事な話はコーチとか部長を介さず、直接伝えるようにしています」
そう言えば、大阪桐蔭を破った大阪大会の決勝では、直後に行われた胴上げで土井監督は100キロを超える体を部員に持ち上げられ、そのまま落とされるというシーンがあった。これこそが信頼関係の証だろう。
少子化や競技の多様化などでそれでなくても野球離れが進んでいる。今回の暴力事案を徹底的に検証し、今後に生かさねば手遅れになる。名門のPL学園は2013年に起きた野球部寮内での集団暴力事件による対外試合禁止処分から寮が廃止され、新入部員の募集が停止され、3年後の休部へと追い込まれた。指導者講習会や部員同士の話し合いの場を常日頃から設け、風通しを良くする。必要なのは行き過ぎた行為ではなく、節度のある人間関係を築くことだろう。
(文責・山本智行/スポーツライター)