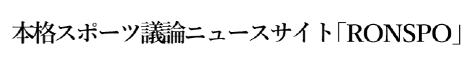追悼…釜本邦茂さんが残した一流ストライカーの定義「失敗しても何回でもシュートにトライできる勇気以外にない」…街中の人混みで鍛えたドリブル技術
「左手を不自由なく使えるようになれば、左足のキックも必ず上達すると思い込んだんです。中学のときの数学の先生が、黒板に右手で数字を書きながら左手で図を描いていたことを思い出したのが根拠と言えば根拠ですね。下宿先の部屋で暇な時間に、左手に持った箸でビー玉をつかんで何個も何個も移動させる。そのうちに左手でご飯を食べられるようになりました。不思議なことに、日本リーグでの通算100ゴールも通算200ゴールも、全部左足で決めましたからね」
他にも高田馬場駅と練習グラウンドのある東伏見駅とを往復する西武新宿線内で、つり革を使わずに揺れる車内で立ち続けて足腰を鍛えた。都会の雑踏を歩くときには、正面から来る通行人との距離が1.5メートルになった瞬間にパッとよける奇異な行動を繰り返した。奇異に映る仕草も、もちろんサッカーに通じている。
「ドリブルで相手を抜くときに、相手の2メートル手前でフェイントを仕掛けてもまったく意味がない。1.5メートルの際どい距離で仕掛けることができるかどうか。その間合いを体に覚えさせていたんですよ」
小学生のときに出会い、京都府立山城高から早稲田大、JSLのヤンマーディーゼル(現セレッソ大阪)とボールを追い続け、40歳だった1984年に現役を引退するまでサッカーを純粋に愛し続けた軌跡が、言葉の端々から伝わってくる。
キャリアのなかで最大の勲章が1968年のメキシコ五輪で獲得した銅メダルであり、日本が6試合であげた総得点9のうち7ゴールを決めて手にした大会得点王となる。7ゴールの内訳は右足が4、ヘディングが1、鍛え上げた左足が2だった。
実は日本の残る2ゴールをアシストしたのも釜本さんだった。日本の全得点に絡んだ実績が時代を超えて“熱き”メッセージと化してきた。自身の2アシストは最初から意図したものではなかった、と明かした釜本さんはこう続けている。2000年のシドニー五輪直前に、トルシエジャパンへの提言をインタビュー取材したときだった。
「アシスト、アシストと考えている選手は単なる配球役で、実はそれほどアシストを決められない。点を取りにいく選手がアシストも決められる。シュートを打たれると怖いから相手選手が飛び込んでくる。そうなればパスを通せるスペースが生まれる。勝つために何が必要か。やはりシュートを打とうとしないとダメなんです。そして、ゴールを決める選手がストライカーと呼ばれる。2列目の選手、もっと言えば最終ラインの選手でも、ゴールを決め続ければストライカーです。フォワードの選手がストライカーとなるための条件は、それは失敗しても何回でもシュートにトライできる勇気以外にない」
釜本さんがストライカーの定義を熱く語ってくれてから四半世紀。戦術やポジションごとに課されるタスクなどが刻々と変貌を遂げても、国際Aマッチ出場76試合で日本歴代最多の75ゴールを決めた偉大なストライカーが抱き続けたイズムは、時空を超えたメッセージとして日本サッカー界に受け継がれていく。
(文責・藤江直人/スポーツライター)