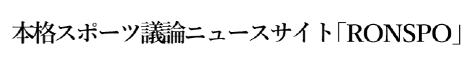箱根駅伝予選会の集団走はもう古い? トップ通過を果たした中央学大が今回から“定番”の集団走をやめた深い理由とは?
神奈川大も同時期から集団走を用いており、集団走は箱根駅伝予選会でスタンダードな戦い方になった。今大会でも多くの大学が採用している。例えば日体大は、平島龍斗と田島駿介(ともに4年)を単独走で行かせて、残り10人は「キロ3分02秒」設定で集団走を実施。10㎞通過が19位と前半は出遅れるかたちになったが、「レースは予定通りで
した。学生を信じていましたし、終盤上げてくれるだろう、と思っていました。戦略通りです」と玉城良二駅伝監督。後半に順位を上げて、チームは78年連続出場を決めた。
これは集団走が功を奏した例になるだろう。
一方、終盤に圏外へ弾きだされた法大、専大も集団走を取り入れていたが、うまくいかなかった。
今回、集団走の先駆者といえる中央学大がその戦術を捨てて臨んだ。どんな理由があったのだろうか。
「集団走を行うと、途中で飛び出したいとか、やりたいことできない子が出てくる。自己主張の強い選手もいますし、それなら各自で走った方がいい。ダメだったら自己責任ですよ(笑)。また、いつもうちは他校のペースメーカーになってしまうことが多いので、そうならないようにというのも理由のひとつです」(川崎監督)
今回、通過を決めたある大学の指揮官は、集団走をする選手たちに、「自分たちで引っ張るのではなく、いい集団を見つけて、そこについていくように」という指示を出している。同じ集団走でもチーム内で明確にペースを決めて臨む大学と、他校のペースメイクをうまく利用して、集団で走る大学があるのだ。集団走のイメージが強く、フラッ
シュイエローの目立つユニフォームを着ている中央学大はライバル校から〝ターゲット〟にされることが多かった。
集団走から単独走に切り替えることになり、川崎監督は、「自分の走りやすい集団や個人を見つけて、一緒にいくように指示を出しました。また、これまでは15㎞以降に順位を落とすことが多かったので、公園内の折り返し(17.4㎞地点)をまわってから頑張ろう、と。そこまではとにかく脚を残すように。それだけです」と細かな指示は出さなかった。
3週間前に集団走をやらないことを告げられると選手間では動揺があったという。
「3年間、いかにミスなくゴールできるかという感じでやっていたので、正直びっくりしました」と主将・近田陽路(4年)も驚いたようだ。しかし、川崎監督の意図を理解した選手たちは堂々としたレース運びを見せる。近田は1時間02分04秒で個人7位。昨年の吉田礼志(現・Honda)に続いて、中央学大が2年連続で日本人トップを輩出した。そしてチームも川崎監督の指示通りに終盤ペースアップ。順大と山梨学大を逆転して、堂々のトップ通過を果たした。
予選会の1位は第84回大会以来18年ぶりだ。このときは本戦で過去最高の総合3位に食い込んでいる。